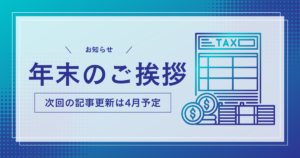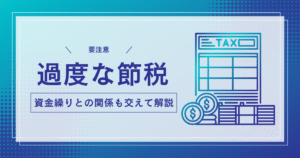【103万円の壁が変わる!】2025年度(令和7年度)税制改正(所得税)
この記事を読むのに必要な時間は約7分です。
具体的な影響も含めて解説
POINT
- 基礎控除及び給与所得控除の最低保障額の引上げにより、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」へと改正!
- 特定親族特別控除の創設で、子(大学生)の給与収入が150万円以下であれば、親の方で改正前の扶養控除と同額の特定親族特別控除が適用可!
- パートで働く妻やアルバイトの大学生は、税金の壁だけでなく、社会保険関係の壁である「年収106万円の壁」や「年収130万円の壁」も意識して働き方を考える必要あり!
いわゆる「103万円の壁」への対応
令和7年度税制改正法が令和7年3月31日に国会で可決・成立しました。その中でも特に影響がある、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」となった改正について、パートで働く配偶者やアルバイトの大学生がいるご家庭にどのような影響があるかも含めて解説します。
改正前の「103万円の壁」は、パートで働く妻やアルバイトの大学生が給与収入103万円を超えると所得税が発生してしまうことから、103万円以下となるように日数や時間を調整するという問題点がありました。また、昨今の賃金上昇も就業調整を更に後押ししてしまい、これが人手不足の一因にもなっていることから、今回の改正に至りました。
改正内容
①基礎控除の引上げ
合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額が58万円(改正前:48万円)に引上げられ、合計所得金額655万円以下については基礎控除の特例により更に上乗せ加算されることとなりました。
なお、合計所得金額132万円以下の基礎控除額の加算(37万円)は恒久措置であるものの、合計所得金額132万円超~655万円以下の層の上乗せ加算(30万円・10万円・5万円)は、令和7年分及び令和8年分のみの期間限定とされました。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
【所得税】
| 改正前 | 改正後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 合計所得金額 | 控除額 | 合計所得金額 (給与収入の目安) | 令和7・8年分 控除額 | 令和9年分~ 控除額 |
| 132万円以下 (給与収入200万円相当以下) | 95万円 (37万円上乗せ) | 95万円 | ||
| 132万円超~336万円以下 (給与収入200万円相当~475万円相当以下) | 88万円 (30万円上乗せ) | 58万円 | ||
| 336万円超~489万円以下 (給与収入475万円相当~665万円相当以下) | 68万円 (10万円上乗せ) | 58万円 | ||
| 489万円超~655万円以下 (給与収入665万円相当~850万円相当以下) | 63万円 (5万円上乗せ) | 58万円 | ||
| 655万円超~2,350万円以下 (給与収入850万円相当~2,545万円相当以下) | 58万円 (上乗せなし) | 58万円 | ||
| 2,400万円以下 | 48万円 | 2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 | 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 | 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
【個人住民税】
個人住民税の基礎控除額については、現行の43万円から改正はありません。
②給与所得控除の引上げ
会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与収入から控除できる概算経費(給与所得控除)があります。今回の改正では、この給与所得控除が昨今の物価上昇及び就業調整への対応のため、最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引上げられました。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
【所得税】
| 改正前 | 改正後(令和7年分~) | ||
|---|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 55万円 | 給与所得控除の最低保障額 65万円 |
【個人住民税】
個人住民税についても、令和8年度分以後から給与所得控除の最低保障額が65万円に引上げられます。
③特定親族特別控除の創設
大学生年代(19歳以上23歳未満)の子がいる親が扶養控除を受けるためには、改正前は子の給与収入が103万円以下でなければ適用ができませんでした。今回の改正で、令和7年分より子の給与収入が150万円以下であれば、改正前の扶養控除と同額の特定親族特別控除を受けられるようになりました。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
・子の給与収入が123万円以下⇒親の方で扶養控除が適用
・子の給与収入が123万円超~188万円以下⇒親の方で特定親族特別控除が適用
【所得税】
| 所得控除 | 子などの合計所得金額 (給与収入の場合) | 親などの控除額 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 扶養控除(特定扶養親族) | 48万円以下 (給与収入103万円以下) | 63万円 | 63万円 |
| 48万円超~58万円以下 (給与収入113万円超~123万円以下) | 0円 | ||
| 特定親族特別控除 | 58万円超~85万円以下 (給与収入123万円超~150万円以下) | 63万円 | |
| 85万円超~90万円以下 (給与収入150万円超~155万円以下) | 61万円 | ||
| 90万円超~95万円以下 (給与収入155万円超~160万円以下) | 51万円 | ||
| 95万円超~100万円以下 (給与収入160万円超~165万円以下) | 41万円 | ||
| 100万円超~105万円以下 (給与収入165万円超~170万円以下) | 31万円 | ||
| 105万円超~110万円以下 (給与収入170万円超~175万円以下) | 21万円 | ||
| 110万円超~115万円以下 (給与収入175万円超~180万円以下) | 11万円 | ||
| 115万円超~120万円以下 (給与収入180万円超~185万円以下) | 6万円 | ||
| 120万円超~123万円以下 (給与収入185万円超~188万円以下) | 3万円 | ||
【個人住民税】
個人住民税についても改正があり、令和8年度分以後から適用されます。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
| 所得控除 | 子などの合計所得金額 (給与収入の場合) | 親などの控除額 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 扶養控除(特定扶養親族) | 48万円以下 (給与収入103万円以下) | 45万円 | 45万円 |
| 48万円超~58万円以下 (給与収入113万円超~123万円以下) | 0円 | ||
| 特定親族特別控除 | 58万円超~95万円以下 (給与収入123万円超~160万円以下) | 45万円 | |
| 95万円超~100万円以下 (給与収入160万円超~165万円以下) | 41万円 | ||
| 100万円超~105万円以下 (給与収入165万円超~170万円以下) | 31万円 | ||
| 105万円超~110万円以下 (給与収入170万円超~175万円以下) | 21万円 | ||
| 110万円超~115万円以下 (給与収入175万円超~180万円以下) | 11万円 | ||
| 115万円超~120万円以下 (給与収入180万円超~185万円以下) | 6万円 | ||
| 120万円超~123万円以下 (給与収入185万円超~188万円以下) | 3万円 | ||
具体的な影響
上記の改正により、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、所得税がかからない給与収入額が103万円(基礎控除額48万円+給与所得控除55万円)から160万円(基礎控除額95万円+給与所得控除65万円)へ拡大され、いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」となりました。
①パートで働く妻とその夫はどうなる?
パートで働く妻
・「所得税」がかからない給与収入額⇒「103万円(改正前)」から「160万円(改正後)」へ引上げられる。
・「個人住民税」がかからない給与収入額⇒「100万円(改正前)」から「110万円(改正後)」へ引上げられる。
※市区町村によって収入要件が異なる場合あり
パートで働く妻をもつ夫
・配偶者控除を受けられる配偶者(妻)の給与収入額⇒「103万円(改正前)」から「123万円(改正後)」へ引上げられる。
・配偶者(妻)の給与収入額が123万円を超えても、160万円以下であれば配偶者特別控除により配偶者控除と同額の控除を受けることができる。
その後、妻の給与収入額に応じて段階的に配偶者特別控除額は減り、201万円を超えると控除額は0円となる。
<まとめ>
| 妻の給与収入額 | 妻の税金 | 夫の配偶者(特別)控除 (所得税) | |
|---|---|---|---|
| 個人住民税 | 所得税 | ||
| 110万円以下 | 発生しない | 発生しない | 配偶者控除(38万円) |
| 110万円超~123万円以下 | 発生する | ||
| 123万円超~160万円以下 | 配偶者特別控除(38万円) | ||
| 160万円超~201万円以下 | 発生する | 配偶者特別控除(36万円~3万円) | |
| 201万円超 | 配偶者特別控除なし(0円) | ||
②アルバイトの大学生(19歳以上23歳未満)とその親はどうなる?
アルバイトの大学生
・「所得税」がかからない給与収入額⇒「103万円(改正前)」から「160万円(改正後)」へ引上げられる。
・「個人住民税」がかからない給与収入額⇒「100万円(改正前)」から「110万円(改正後)」へ引上げられる。
※市区町村によって収入要件が異なる場合あり
アルバイトの大学生をもつ親
・アルバイトの大学生の給与収入額が150万円以下であれば、特定親族特別控除により扶養控除と同額の控除を受けることができる。
その後、子の給与収入額に応じて段階的に特定親族特別控除額は減り、188万円を超えると控除額は0円となる。
<まとめ>
| 子(大学生)の給与収入額 | 子(大学生)の税金 | 親の扶養控除・特定親族特別控除 (所得税) | |
|---|---|---|---|
| 個人住民税 | 所得税 | ||
| 110万円以下 | 発生しない | 発生しない | 扶養控除(63万円) |
| 110万円超~123万円以下 | 発生する | ||
| 123万円超~150万円以下 | 特定親族特別控除(63万円~3万円) | ||
| 150万円超~160万円以下 | |||
| 160万円超~188万円以下 | 発生する | ||
| 188万円超 | 特定親族特別控除なし(0円) | ||
最後に
令和7年度(2025年度)税制改正は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ、特定親族特別控除などが盛り込まれ、大きな影響を及ぼす改正となりました。
パートで働く配偶者やアルバイトの大学生については、上記の税金の壁だけでなく、社会保険関係の壁である「年収106万円の壁」や「年収130万円の壁」も意識して働き方を考える必要があります。詳細は以下の記事をご覧下さい。
【知らないと損する】年収の境界線「○○万円の壁」!
https://www.okaniwa-tax.com/income-thresholds/
- 当事務所の顧問先様で、上記の内容でご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい!
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。