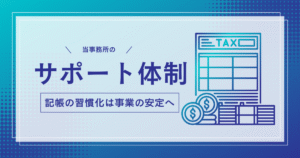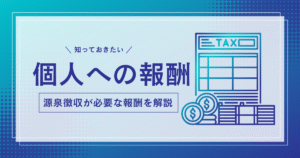【初心者向け】源泉徴収とは?カラクリを具体例でスッキリ解説|法人の義務と個人の精算まで
この記事を読むのに必要な時間は約3分です。
制度の仕組みを具体例も交えて解説
POINT
- 源泉徴収は、給与や報酬などの支払時に、支払う側(会社など)があらかじめ所得税を差し引いて国に納める制度!
- 法人の立場からすると、源泉徴収義務者として給与や報酬の支払い時に一定額を天引きして国に納める必要あり!
- 従業員や個人事業主の立場からすると、源泉徴収で引かれている金額は「所得税の前払い」のようなもので年末調整や確定申告で精算!
源泉徴収とは
源泉徴収を一言で言うと、法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)が「従業員への給与」や「個人への一定の報酬(※)」の支払時にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める制度です。
本記事では、法人が「従業員への給与」や「個人事業主への報酬」を支払う際の源泉徴収の仕組みを解説します。
(※)個人への全ての報酬が源泉徴収の対象ではないため、一定の報酬と記載しています。詳細は次回の記事で解説します。
法人の立場(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も含む)
法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)は「源泉徴収義務者」として、「従業員への給与」や「個人事業主へ一定の報酬(※)」を支払うときに所得税を天引きし、国に納めなければなりません。支払う相手が法人であれば、基本的に源泉徴収は不要です。
個人事業主へ報酬を支払う場合、支払額が100万円以下であれば10.21%を源泉徴収する必要があります。
具体例
原稿料11万円(税込)を個人事業主へ支払う場合
- 報酬金額:110,000円(うち消費税10,000円)
- 源泉徴収税額:10,210円(100,000円×10.21%)
- 支払金額:99,790円(110,000円-10,210円)
→差し引いた源泉徴収税額10,210円は、原稿料を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付を行うこととなります。
給与を受け取る従業員・報酬を受け取る個人事業主の立場
【給与を受け取る従業員の場合】
従業員は毎月の給与から所得税を差し引かれた金額を受け取り、年末に会社が「年末調整」を行うことで1年間の所得税額と天引き済みの税額を精算します。
具体例
従業員が給与30万円を法人から受け取る場合
- 給与額:300,000円
- 源泉徴収税額:6,850円(源泉徴収税額表に当てはめて算出)
- 受取金額:293,150円(300,000円-6,850円)※社会保険料などは割愛
→毎月の給与から差し引かれた所得税は、年末に会社が行う「年末調整」で精算されます。例えば、年末調整で1年間の所得税が7万円と確定し、既に毎月の給与から82,200円(6,850円x12ヶ月)が天引きされている場合、差し引かれ過ぎている12,200円が戻ってきます。
【報酬を受け取る個人事業主の場合】
個人事業主が法人から報酬を受け取る場合、報酬の支払時に10.21%が源泉徴収されます。
具体例
個人事業主が原稿料11万円(税込)を法人から受け取る場合
- 報酬金額:110,000円(うち消費税10,000円)
- 源泉徴収税額:10,210円(100,000円×10.21%)
- 受取金額:99,790円(110,000円-10,210円)
→差し引かれた源泉徴収税額10,210円は「所得税の前払い」のようなものであり、確定申告で1年間の所得税を計算し、前払い分(源泉徴収済み分)を差し引いて精算します。
源泉徴収の義務は支払者側(法人など)であり、請求書を発行する側ではありません。そのため、個人事業主が発行する請求書に源泉徴収税額が記載されていない場合でも、法人側で源泉徴収税額を計算し、請求金額から差し引いて支払うケースがあります。このため、請求金額と実際の入金額が一致しないことがありますので、必ず確認するようにしましょう。
最後に
源泉徴収は、法人(従業員を雇用して給与を支払う個人事業主も)にとっては源泉徴収義務者として税金を国へ納める義務があり、個人にとっては税金をあらかじめ支払う前払いのようなイメージです。少し複雑に感じるかもしれませんが、仕組みを知っておくと給与明細や確定申告の理解がぐっと深まります。
- 当事務所の顧問先様で、上記に関してご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい!
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。