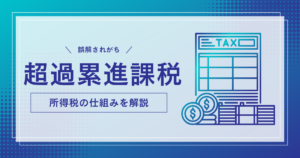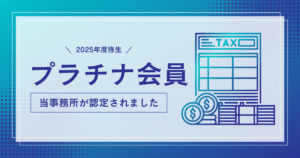【どちらがお得?】「給与」は損?「外注費」にするための要件とは…
この記事を読むのに必要な時間は約3分です。
「外注費」と「給与」の違いや判断基準を解説
POINT
- 「外注費」と「給与」は取扱いが大きく異なる!報酬を支払う側は「外注費」の方が有利!受取る側は「給与」の方が有利!
- 契約形態のみの形式面だけで判定せず、5つの判断基準を総合的に勘案して判定することが重要!
- 「外注費」として計上したものが「給与」と指摘されないようにするため、契約書を作成の上、判断基準を意識して運営することが重要!
取扱いが大きく異なる
個人へ支払う報酬が「外注費」でも「給与」でも、いずれで計上しても経費にはなるものの、どちらに該当するかで源泉徴収や消費税、社会保険加入義務で取扱いが大きく異なります。意外と判断に迷うケースもあり、税務調査でもよく問題となる論点ですので、今回はこちらについて解説していきます。
「外注費」と「給与」の違い
| 項目 | 外注費 | 給与 |
|---|---|---|
| 源泉徴収 | 基本的には不要(一部例外あり) | 必要 |
| 消費税 | 課税取引(控除可) | 不課税取引(控除不可) |
| 社会保険加入 | 不要 | 必要 |
○支払う側の視点
「外注費」として取扱う方が有利となります。
源泉所得税を徴収する義務がなく、支払った消費税が消費税の計算で控除可能であり、社会保険料の負担がありません。
〇受取る側の視点
「給与」として取扱う方が有利となります。
外注費とした場合、確定申告を行う必要があり、基本的には消費税の納税義務が発生し、社会保険も自ら加入する必要があります。
「外注費」か「給与」かの判断基準
「外注費」か「給与」かは勝手に決めて良いものではなく、国税庁の情報より下記の5つの判断基準を総合的に勘案して判定を行います。「請負契約だから外注費」、「雇用契約だから給与」と形式的に判定することのないよう注意が必要です。
| 判断基準 | 外注費 | 給与 |
|---|---|---|
| 他人が代替して業務遂行又は役務提供ができるかどうか(代替性)。 | 代替可 | 代替不可 |
| 報酬の支払者から作業時間を指定、報酬が時間単位で計算など時間的な拘束を受けるかどうか(拘束性)。 | 拘束なし | 拘束あり |
| 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか(指揮監督)。 | 指揮監督なし | 指揮監督あり |
| 完成品が不可抗力で滅失などした場合、既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか(報酬請求権)。 | 請求不可 | 請求可 |
| 材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか(材料又は用具等の供与)。 | 供与なし | 供与あり |
「外注費」を「給与」と指摘されないためのポイント
- 契約書の作成
上記の判断基準を意識して契約書を作成し、実務上も外注費となるよう(給与として指摘されないよう)運営することが望ましいです。消費税の表示も税込での記載を避けて、外税表示で計算するとより良いものと思われます。 - 外注先が確定申告をしているかの確認
支払先である個人が、受取った報酬について確定申告をしていない場合には給与と指摘される可能性がありますので、念のため外注先が確定申告をしていることを確認することが望ましいです。
最後に
「外注費」と「給与」は、国税庁によると上記の5つの要素を総合的に判断するとされており、少し曖昧な判断基準となっています。しかし、この判断を誤ると源泉徴収や消費税、社会保険加入義務などの取扱いが異なるため、申告内容に大きな影響が出てきてしまいます。
過去の判例として、一人親方へ支払った報酬が外注費ではなく、給与と認定された事例もあります。これは、職人の作業が指揮監督の下に提供され、独立した仕事と認められなかったことと、報酬の支払いを基本賃金や時間外手当などを基準に支払われていたこととが原因となっています。
外注費で処理をする場合は、上記のポイントを抑え、給与ではないということをしっかりと整理しておくことが重要となります。
- 当事務所の顧問先様で、上記に関してご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい!
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。